テンコです!
離婚後、どこに住むかどうやって決めればいいか分からない。。。
そんな風に悩んでいませんか?
子連れ離婚の場合、子どもの心理面などへの配慮も必要なため、なかなか判断がしづらいと思います。
離婚後は実家に戻る方も多いですが、いいことばかりとは行かないのが現状のようです。
今回は、離婚後の生活拠点の決め方の判断ポイントについて解説します。
それぞれ置かれている環境や関係性も違うので、何ばベストかは人それぞれです。ですが、配慮すべきポイントなどを考えた上であなたなりの優先順位をつけることができたらと思います。
具体的には次のとおりです。
- 子どもの年齢に応じた配慮
- 経済的なこと
- 人間関係
- 仕事や学校のこと
- 将来を見据えた長期的視点
 テンコ
テンコあなたなりの優先順位が明確になれば、自ずと答えが見つかるはずです。
子どもの年齢に応じた配慮すべきポイント


何より優先したいのは、子どもの事。お子さんの年齢によって配慮すべき点が違います。
幼児
未就学児はとにかく生活のサポートが欠かせません。
小さいウチは体調を崩すことも多いので、支援を受けられる環境があると助かります。
実家や行政の育児サポートなどを視野に入れて検討した方が良さそうです。
小学生
小学生にもなると、友達などのコミュニティができているので、大幅な環境変化は避けたい所です。



とはいえ苗字が変わるなど、注目されるのを気にしている場合は、長期休暇を利用して引越しする方も多いです。
放課後は子どもだけで過ごす可能性が高いので、児童クラブや習い事など、親の不在時の居場所を確保できると安心です。
中高生
通学面でのアクセスを考慮する必要があります。
受験を控えている時期であれば、転居のタイミングを慎重に選ばなければなりません。
個人として尊重し、プライベート空間を確保します。
経済面からの判断材料
住居費は金額が大きいので、無理のない範囲で選びたいところですが、考慮すべき点は次のとおりです。
実家に戻るメリット•デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 経済的な負担が軽くなる 育児サポートが受けられる 精神的な安心感 生活の立て直しがしやすい | 親との価値観の違い・干渉 遠方に引越しの可能性 経済的自立が遅れるリスク 親の高齢化リスク |
離婚後の精神的ダメージや子育ての負担は、関係性の良い実家であればかなり軽減されそうです。
一方で、親との関係性が良くない場合や、高齢の場合は別の問題が発生する可能性があります。



生活再建まで「一時的に」実家を頼るくらいが適度な距離感かもしれませんね。
賃貸を借りる場合の注意点
賃貸を借りるのであれば、家賃・間取り・アクセス・セキュリティなどを考慮して選びます。
シングルマザーでは審査が通りにくいなどとも言われていますが、家賃を滞納しない信頼を証明できれば問題なく借りれます。
詳しくはパートタイマーのシングルマザーが賃貸を借りるときの完全ガイドで解説しています。
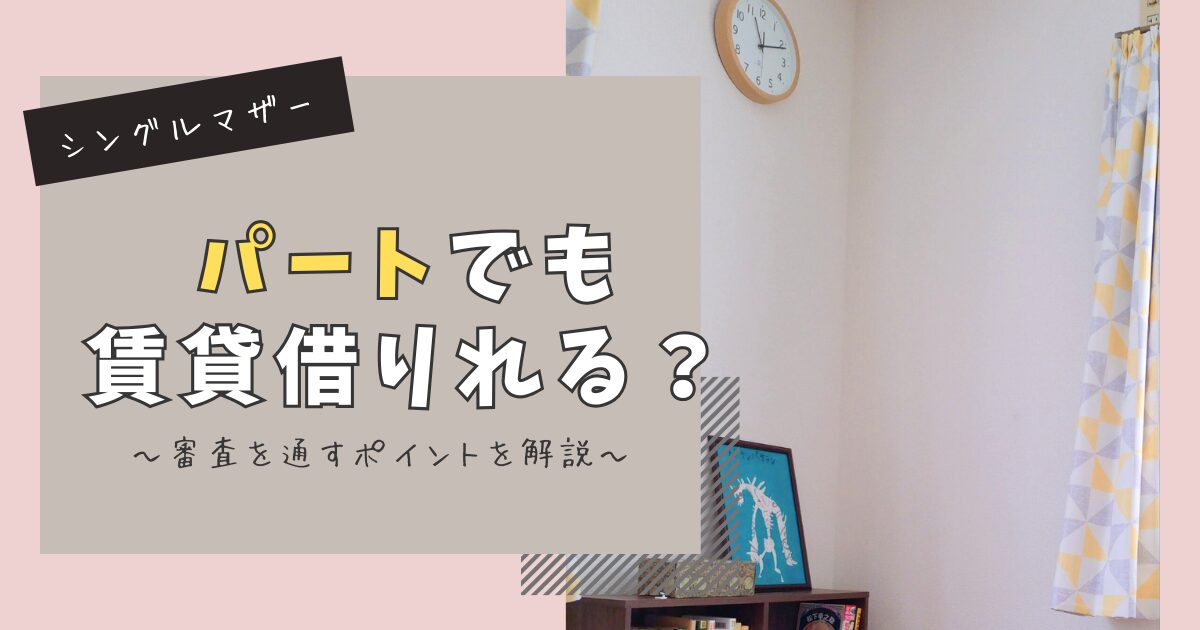
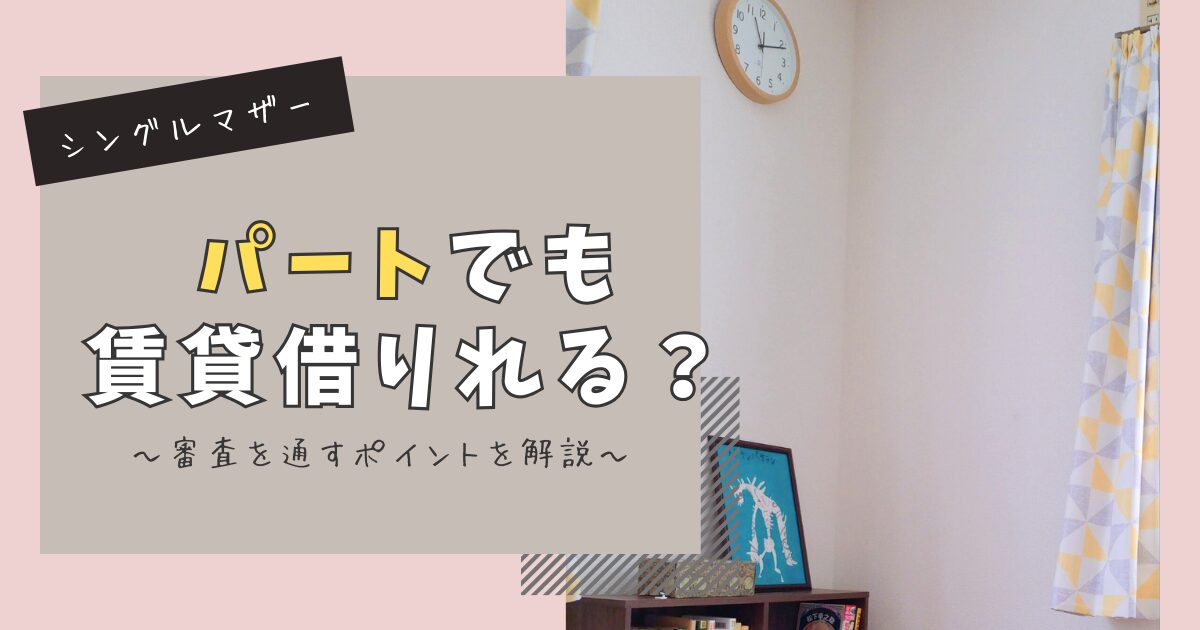
持ち家に残る場合の住宅ローンや名義の問題
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 住みなれた場所で生活できる 家賃が不要(完済してる場合) 不動産として資産価値がある | 住宅ローン返済リスクが続く 元夫名義だと、滞納リスクに巻き込まれる 固定資産税や修繕費など維持費がかかる 元夫名義だと、将来売却・相続トラブルの可能性 |
持ち家に住み続けるなら、自分名義にしておく方が後々のトラブル回避できます。
取り決めた内容は、しっかり公式文書に詳細を記しておきましょう。



持ち家に残るメリットはあまりないように思いますが。。。
人間関係からの視点


心理的な安心感は、やはり人間関係に大きく左右するところだと思います。
例えば引越しで環境がガラッと変わった場合でも、安心できる人がそばにいてくれるのは心強いはず。
実家との関係
関係性が良い実家であれば、これ以上ない心強い味方です。
精神的ダメージを受けた離婚後しばらくは、少し甘えさせてもらって、再起に向けたエネルギーを蓄えることも必要です。
元夫との距離
子どもとの面会交流を考えているのであれば、あまり遠くだと不便です。



逆にあまり接触させたくない関係であれば、不便ゆえに接触が減る可能性があります。
新しい土地での人間関係・孤独感
誰だって、一から関係性を作るのにはストレスがかかります。
全く知り合いのいない場所よりも、親族や友人が近い場所の方が安心です。
過度なストレスから、鬱になる可能性も否定できないので、可能性がある方は特に注意です。
仕事・学校との関係


職場への距離、通勤時間の短縮
子どもの発熱によるお迎えや、部活や塾の送迎などを考えると、通勤距離が遠いと負担が大きくなります。
交通費の面からも近いと負担が軽減されます。
子どもの学校・習い事の継続性
自分の帰宅より子どもの帰宅が早いケースも多いので、学校との距離が遠いと心配ですよね。
また、学童を利用する場合や習い事を継続する場合は、そちらのアクセスも考慮する必要があります。
将来を見据えた長期的視点


将来を見据えた長期的なビジョンがあると、判断しやすくなります。
子どもの進学や就職のしやすさ
近隣に塾や予備校、図書館など教育資源が少ないなど、地方や郊外だと選択肢が限られる場合があります。
就職に関しても同じように、選択肢が限られるため、結果として「進学や就職のために再度引っ越し」が必要になることもあります。
親の高齢化・介護リスク
子育て世代だと、親の手を借りるのは本当に助かりますが、一方で親の高齢化によるケアも同時に発生する可能性があります。
そうなると、働き方に制限がかかったり、将来的に再婚や転居が難しくなるリスクもあります。
自分自身のキャリアや再婚の可能性
自分の事が後回しになりがちですが、まだまだキャリアアップや再婚の可能性もあります。
一時的に生活再建のために我慢することが必要ですが、将来的なビジョンを描き、可能性を閉じ込めないようにしたいですね。
今後のスキルアップについては40代シングルマザーにオススメの資格|働きながら取得するなら?でおすすめ資格を紹介しています。
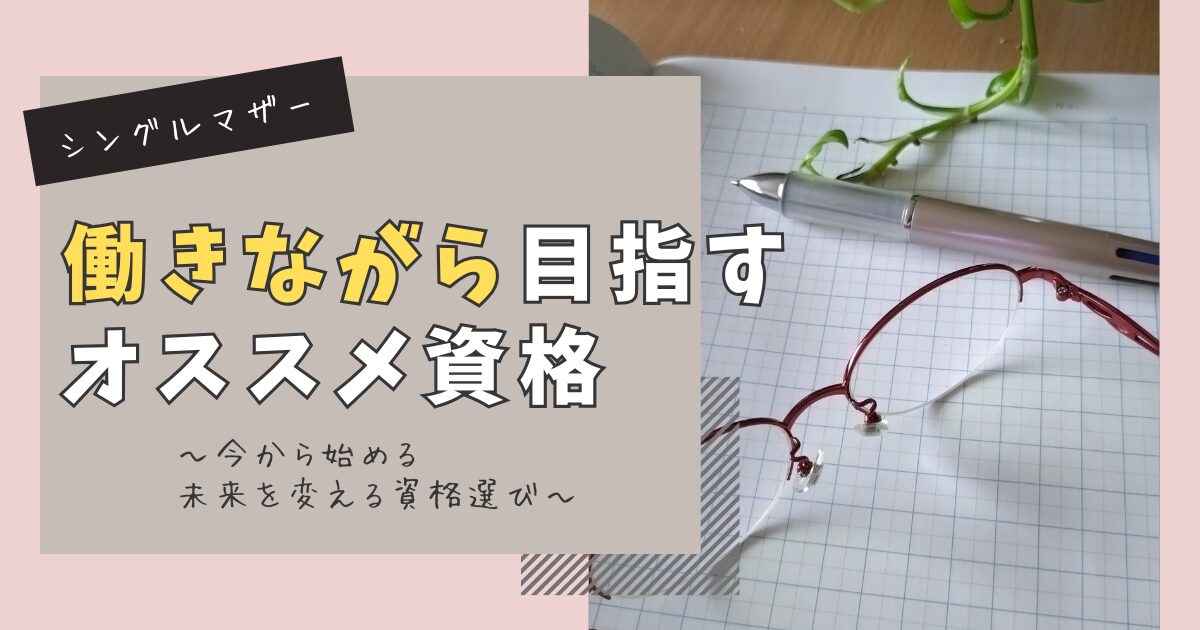
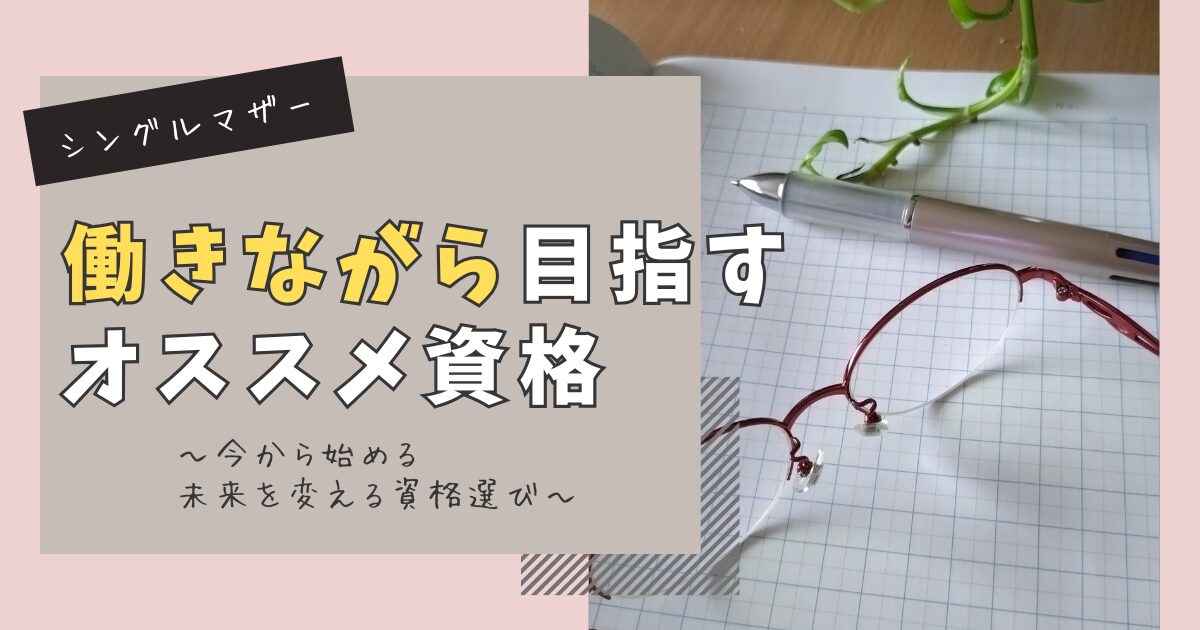
地域の支援制度や福祉サービス
地域による行政サービスの若干の違いはあります。
子育て世代は、病児保育や学童保育の利用しやすさなど子ども向けサービスが充実していると助かります。
まとめ|


最後におさらいです。
- 子どもの年齢に応じた配慮
- 経済的なこと
- 人間関係
- 仕事や学校のこと
- 将来を見据えた長期的視点
離婚後は、子どものことを全て自分ひとりで背負わなければならなくなるので、できるだけ自分に負担の少ない選択肢を取るのがいいです。
とはいえ、そんな都合の良い選択肢がすぐに見つかる訳ではないのが現実。
自分と子どもにとって、何が一番優先される事項なのか、今回解説した懸念点を把握した上で判断されるといいと思います。



一度決めたら「絶対」ではなく、その時々で変わっていくものだと思うので、考えすぎないで!
参考になれば嬉しいです。
ではでは。
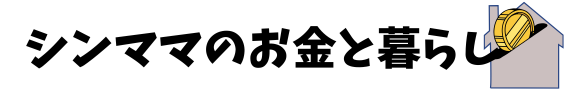

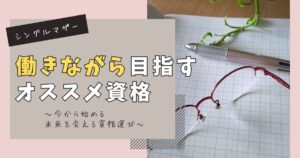

コメント